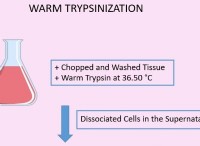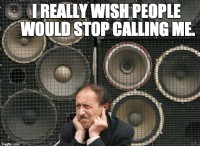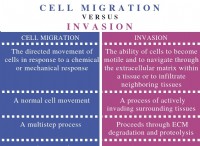ヒトデとしても知られる海の星は、ムール貝、フジツボ、ウニなどの獲物種の個体数を制御することにより、海洋生態系のバランスを維持する上で重要な役割を果たします。それらの減少は、食物連鎖を混乱させ、魚、海鳥、海洋哺乳類などの他の海洋生物にカスケード効果をもたらす可能性があります。
特に、北米の太平洋沿岸沖で発見されたヒマワリの海の星(ピクノポディア・ヘルアントゥイデス)は、海の星消耗症候群として知られる病気のために2013年以来、大幅な人口減少を経験しています。この疾患の正確な原因はまだ研究されていますが、研究によると、気候変動による海洋温暖化は、症候群の原因となる病原体の増殖のための好ましい状態を生み出します。
気候変動の影響を受ける別の種は、太平洋岸北西部沿岸に沿って一般的な黄土色の海の星(ピサスター・オクラセウス)です。温暖化の海温は、幼虫の死亡率と発達の異常に関連しており、募集の故障と人口の減少につながります。
ヒトデの個体群の減少には複数の要因が関与している可能性がありますが、証拠は、気候変動が海洋条件を変え、海洋生態系の微妙なバランスを破壊することにより重要な役割を果たしていることを示唆しています。