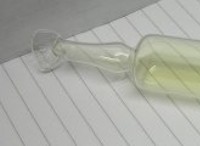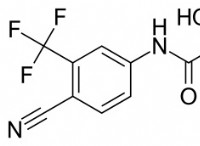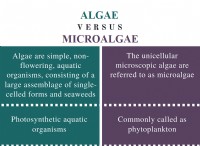1。固体状態 :固体化合物では、成分粒子(原子、分子、またはイオン)は、イオン結合、共有結合、または水素結合などの強力な分子間力によって結合されます。これらの力は、粒子がその位置に固定され、簡単に動くことができない剛性構造を作成します。その結果、電界が適用されると、電流を運ぶために利用可能な遊離モバイルイオンまたは電子はなく、化合物は電気絶縁体として動作します。
2。溶融状態 :化合物がその融点に加熱されると、固体から液体状態への相変化を受けます。融解中、粒子間の分子間の力が弱くなり、粒子はこれらの力を克服し、より自由に動くのに十分な運動エネルギーを獲得します。この移動度の増加により、化合物内のイオンまたは電子が適用された電界に移動して応答することができます。その結果、化合物は溶融状態で電気的に導電性になります。
たとえば、例として、塩化ナトリウム(NaCl)を考慮してください。固体NaClでは、ナトリウム(Na+)と塩化物(Cl-)イオンが強力なイオン結合によって結合され、硬い結晶格子を形成します。この状態では、イオンは動かず、電流を運ぶために動くことができないため、NaClは電気を導入しません。ただし、NaClが溶けると、イオン結合が弱まり、Na+およびCl-イオンが自由に移動できます。この溶融状態では、NaClはそのイオンの可動性のために電気を導入できます。
要約すると、固体化合物と溶融化合物の間の電気伝導率の違いは、その構成粒子の可動性から生じます。固体状態では、強い分子間力が粒子の動きを制限し、電気伝導を阻害します。溶融状態では、分子間力が弱くなると粒子が自由に動くことができ、電流の通過を可能にし、化合物を電気的に導電性にします。