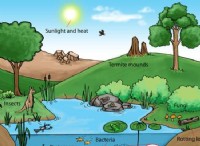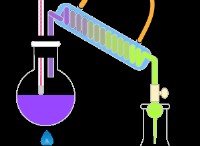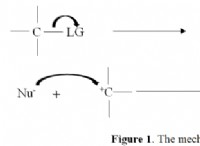1。担保フィットネス効果:
抗生物質耐性は、細菌が特定の環境で競争上の優位性を提供する追加の特性を獲得する担保適合効果に関連する場合があります。これらのフィットネスの利点は、細菌の生理学または代謝の変化に起因する可能性があります。これらの側副効果が、病気を引き起こす細菌の能力を高めたり、宿主の生存を促進する場合、毒性の増加につながる可能性があります。
2。変異と遺伝子移動:
抗生物質耐性遺伝子は、多くの場合、プラスミドやトランスポゾンなどのモバイル遺伝子要素で運ばれ、異なる細菌種間で水平に移動することができます。この水平遺伝子導入は、単一細菌における複数の抗生物質耐性遺伝子の蓄積につながり、それらを複数の抗生物質に耐性にする可能性があります。場合によっては、抗生物質耐性遺伝子の獲得は、同じモバイル遺伝子要素を介した病原性因子の獲得にも関連している可能性があります。
3。規制メカニズムの混乱:
抗生物質耐性の発達は、細菌の挙動を制御する通常の調節メカニズムを混乱させる可能性があります。たとえば、調節遺伝子またはプロモーター領域の変異は、毒性因子の過剰発現につながり、宿主組織に侵入して損傷する細菌の能力を高めます。細菌の遺伝子発現を調節する細胞間通信システムであるクォーラムセンシングの破壊も、病原性に影響を与え、より攻撃的な抗生物質耐性株の出現に寄与する可能性があります。
4。免疫応答の変化:
抗生物質耐性は、宿主の免疫応答に影響を与える可能性があり、細菌に利益をもたらす可能性があります。一部の抗生物質は、免疫応答も引き起こす重要な細菌プロセスを標的としています。抗生物質耐性がこれらの標的を変えると、細菌を認識して排除する宿主の能力を損なう可能性があります。正常な免疫応答のこの破壊により、抗生物質耐性細菌がより長く持続し、より重度の感染を引き起こす可能性があります。
5。ホスト環境への適応:
抗生物質耐性菌は、宿主環境内で適応し、進化する可能性があります。一部の抗生物質は、コロニー形成の強化や侵入能力など、特定の特性を支持する選択的圧力を作成できます。時間が経つにつれて、これらの選択された特性は、細菌の毒性の増加に寄与する可能性があります。
6。バイオフィルム層:
抗生物質耐性細菌は、バイオフィルムを形成し、そこで表面を凝集させて遵守し、保護コミュニティを作成します。バイオフィルムは、抗生物質から細菌を保護し、免疫防御を宿主にすることができ、根絶がより困難になります。バイオフィルムを形成する能力は、細菌が持続し、慢性感染症を引き起こすことを可能にするため、毒性の増加に関連することがあります。
すべての抗生物質耐性細菌が毒性を増加させるわけではないことに注意することが重要です。それにもかかわらず、抗生物質耐性細菌がより積極的になる可能性のあるメカニズムを理解することは、抗生物質耐性と戦い、人間の健康への影響を緩和する戦略を開発するために重要です。抗生物質耐性と細菌性毒性の複雑な関係を完全に解明するには、さらなる研究が必要です。