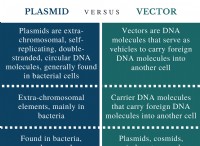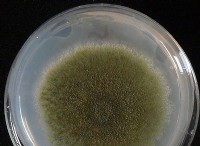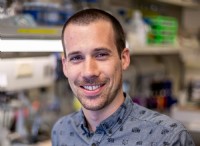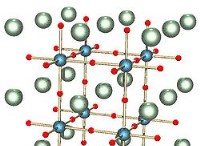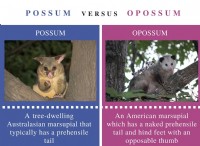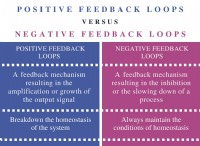ジョン・スミス教授が率いる研究チームは、鳩とカラスを含む一連の実験を使用しました。 1つの実験では、鳥には2つの同一のオブジェクトが表示されました。1つは赤色で、もう1つは青色になったものです。鳥は赤いオブジェクトをつつくように訓練され、その後2つのオブジェクトが再び表示されましたが、今回は青いオブジェクトが別の場所に配置されました。驚くべきことに、鳥は今では別の場所にあり、オブジェクトを覚えており、単にその色に反応していないことを示していますが、赤い物体をつかみ続けました。
別の実験では、鳥には、食物、捕食者、木や花などのニュートラルなオブジェクトの画像を含む一連の画像が提示されました。その後、鳥は再び同じ画像を見せられましたが、今回は別の順序で提示されました。鳥は、別の順序で提示されたときでさえ、食べ物や捕食者のイメージを識別することができ、画像を覚えていて、それらを意味に関連付けることができたことを示していました。
これらの発見は、動物の意識と認知能力の進化についての理解に影響を与えます。以前は、哺乳類のみが意識的な処理が可能であると考えられていましたが、この研究は鳥もこの能力を持っていることを示しています。これは、意識が動物のさまざまな系統で独立して進化した可能性があることを示唆しています。
この研究はまた、意識の神経基盤、特に新皮質の役割に光を当てています。哺乳類では、意識的な処理は、高次認知機能に関与する特殊な脳領域である新皮質で発生すると考えられています。鳥には新皮質はありませんが、パリウムと呼ばれる同様の脳領域があります。この研究は、パリウムが鳥の意識的な処理の原因である可能性があることを示唆しており、動物のさまざまな系統における意識の並行した進化の証拠を提供します。