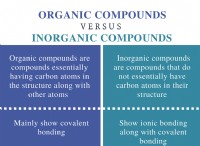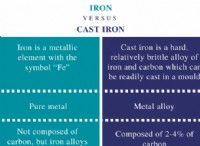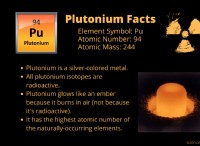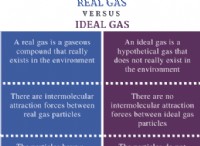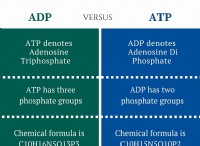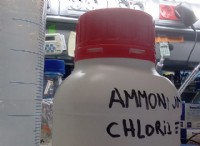1。価電子の数: より多くの価電子を備えた金属は、金属結合が強い傾向があります。これは、より多くの価電子が、積極的に帯電した金属イオンの間で非局在化して共有できるより多くの電子を意味し、凝集性エネルギーと結合強度を増加させるためです。たとえば、アルミニウムには3つの価電子と比較的強い金属結合がありますが、ナトリウムには1つの価電子と弱い金属結合のみがあります。
2。原子サイズ: 原子半径が小さい金属は、金属結合が強い傾向があります。これは、より小さな原子がより密接に詰め込まれているため、電子軌道間のより良いオーバーラップが可能になるためです。オーバーラップの増加は、静電魅力が強く、より安定した金属結合につながります。たとえば、鉄には、鉛よりも原子半径が小さく、金属結合が強いです。
3。結晶構造: 金属の結晶構造は、金属結合の強度にも影響します。顔中心キュービック(FCC)や六角形の密集(HCP)などの密集した結晶構造を持つ金属は、体中心の立方体(BCC)または他の密度の低い構造を持つ金属よりも強い金属結合を持っています。これは、密集した構造が原子のより効率的な梱包を可能にし、電子軌道間のより良いオーバーラップを可能にするためです。たとえば、銅にはFCC構造と強力な金属結合があり、クロムにはBCC構造とより弱い金属結合があります。
4。イオン文字: 一部の金属は、その結合で部分的なイオン性を示し、金属結合の強度に影響を与える可能性があります。金属原子間の電気陰性度の違いが重要な場合、結合はイオン性の特性を引き受ける可能性があり、1つの原子は電子ドナーとして、もう1つは電子受容体として機能します。このイオン特性は、変身電子の数を減らし、正に帯電した金属イオン間の静電反発を増加させるため、金属結合を弱める可能性があります。たとえば、カルシウムは、カルシウムと周囲の電子の間の電気陰性度の違いにより、わずかにイオン金属結合があり、純粋に金属結合と比較して結合を弱めます。
要約すると、金属の金属結合の強度は、原子価電子の数、原子サイズ、結晶構造、イオン特性などの因子によって決定されます。より多くの原子価電子、より小さな原子半径、密集した結晶構造、最小イオン特性を備えた金属は、金属結合が強い傾向があります。