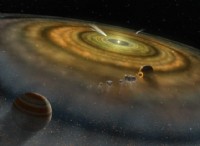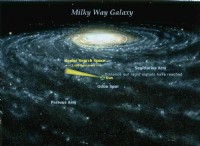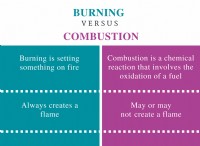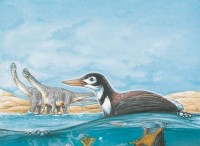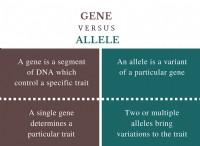1。エリアに精通している :くちばしのクジラは、水中の地形、食品資源、社会的相互作用など、海軍ソナーの周辺の地域に強い精通度があるかもしれません。ソナーによる障害にもかかわらず、彼らは本質的なリソースと親しみやすさを提供するので、彼らはこの地域に戻り続けるかもしれません。
2。限られた生息地オプション :くちばしのクジラには、深海、特定の海洋条件、獲物の入手可能性など、特定の生息地の要件があります。海軍ソナーの周辺のエリアは、他の場所で簡単には見られない適切な生息地を提供する可能性があり、障害にもかかわらずクジラは戻ってきます。
3。コミュニケーションと社会的行動 :くちばしのクジラは、複雑なコミュニケーションと社会的行動で知られています。彼らはエコーロケーションのクリックとホイッスルを使用して、互いにコミュニケーションを取り、社会的絆を維持します。ネイビーソナーの範囲はコミュニケーションを混乱させる可能性がありますが、社会的相互作用を維持し、仲間を見つけるために、彼らはまだその地域に戻るかもしれません。
4。学習と適応 :くちばしのクジラは、環境に学び、適応できる知的な動物です。彼らは最終的にソナーによって引き起こされた障害に耐えるか、適応することを学ぶかもしれないため、課題にもかかわらず地域を使用し続けることができます。
5。人口動態 :個々のくちばしのクジラの行動は、資源の競争や獲物の入手可能性の変化など、人口のダイナミクスの影響を受ける可能性があります。これらの要因は、障害にもかかわらず海軍のソナー範囲に戻るという彼らの決定に貢献する可能性があります。
くちばしのクジラが海軍のソナー範囲に戻る特定の理由は、個人や集団によって異なる可能性があることに注意することが重要です。ソナー障害の行動と潜在的な影響に関与する複雑な要因を完全に理解するには、さらなる研究が必要です。