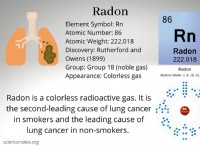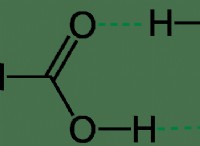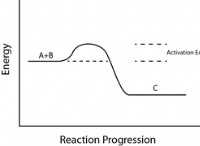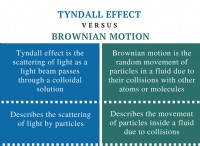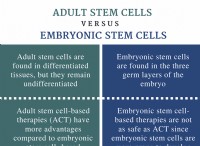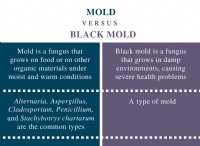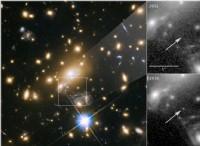1。価電子:価電子の数は、元素がイオンを形成する容易さを大きく決定します。周期表の同じグループ(垂直列)の要素は、同じ数の価電子を共有します。この類似性は、同様のイオン化パターンにつながります。
2。イオン化エネルギー:イオン化エネルギーは、中性原子から電子を除去するために必要なエネルギーです。イオン化エネルギーが低い元素は、電子を簡単に失い、陽性イオン(陽イオン)を形成する傾向があります。グループを下に移動すると、イオン化エネルギーは、最も外側のシェルから電子を除去しやすくなるため、一般的に減少します。
3。電気陰性度:電気陰性度は、原子が電子を引き付ける能力を測定します。電気陰性度が高いほど、原子は電子をそれ自体に引き付けます。期間(水平列)にわたって、一般に電気陰性度は左から右に増加します。電気陰性度が高い元素は、電子を獲得し、陰イオン(アニオン)を形成する傾向が大きくなります。
4。イオン半径:イオン半径とは、イオンのサイズを指します。陽イオンは、通常、電子の喪失により中性の対応物よりも小さいです。一方、アニオンは、より多くの電子を持っているため、中性原子よりも大きいです。イオンのサイズは定期的な傾向に続き、同じ期間の元素が同様のイオン半径を持っています。
5。イオンの安定性:定期的な傾向は、イオンの安定性を予測するのにも役立ちます。一般に、完全な外側の電子シェル(Nobleガス構成)を持つイオンが最も安定しています。たとえば、アルカリ金属(グループ1)は、安定した陽イオンの構成を実現して、安定した陽イオンを形成するために単一の原子価電子を失う傾向があります。ハロゲン(グループ17)は、容易に1つの電子を獲得して外側のシェルを完成させ、安定した陰イオンになります。
6。イオン電荷:イオンの電荷は、得られたまたは失われた電子の数に関連しています。周期表の要素は、グループ番号に対応する電荷でイオンを形成する傾向があります。たとえば、グループ1の要素は1+イオンを形成しますが、グループ2の要素は2+イオンを形成します。
イオンの形成と定期的な傾向を理解することで、科学者は要素の挙動を予測し、反応性や結合などの化学的特性を説明し、周期表で観察されるパターンを合理化することができます。また、特定の特性を持つ材料の設計と、基本レベルでの化学反応を理解するのにも役立ちます。