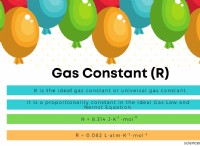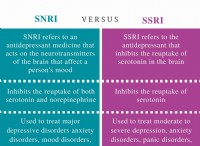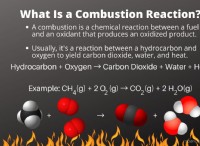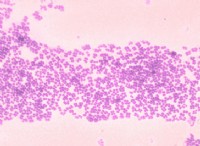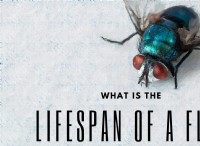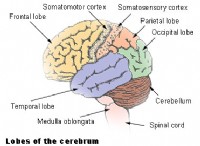1。原子半径: ホウ素ファミリーを下ると、元素の原子半径が増加します。これは、原子価電子が核から遠くにあることを意味し、より弱い静電引力を経験します。その結果、電気陰性度が低下します。
2。有効な核電荷(zeff): Zeffとは、原子価電子が経験する正味の正電荷を指します。核に多くの陽子が追加されるため、グループを下ると増加します。この増加したゼフは、原子核の近くに原子価電子を引き付け、より高い電気陰性度を引き起こします。
3。価電子の数: ホウ素ファミリーの価電子の数は、グループ全体で3つで一定のままです。ただし、これらの原子価電子の配置は変化します。ホウ素の場合、3つの価電子は2秒および2p軌道にあります。グループを下に移動すると、最も外側の価電子はより高いエネルギーレベル(3s、3pなど)を占めます。これらのより高いエネルギーレベルは核から遠くにあり、電気陰性度の低下につながります。
原子半径、効果的な核電荷、および価電子の構成との相互作用は、ホウ素ファミリーの電気陰性度の増加と低下の傾向をもたらします。トレンドの要約は次のとおりです。
-boron(b):小さな原子半径と高いゼフによる高い電気陰性度。
- アルミニウム(AL):原子半径の増加により、ホウ素よりも電気陰性度が低い。
- ガリウム(GA):ゼフの増加により、アルミニウムよりも高い電気陰性度。
-indium(in):原子半径の増加により、ガリウムよりも電気陰性度が低い。
- タリウム(TL):ゼフの増加により、インジウムよりも高い電気陰性度。
この電気陰性度の交互の傾向は、ホウ素ファミリーだけでなく、周期表の他のグループでも観察されます。それは、要素の化学的挙動と特性に関する貴重な洞察を提供します。