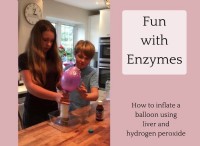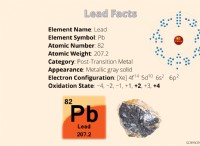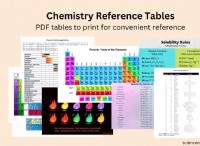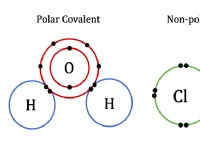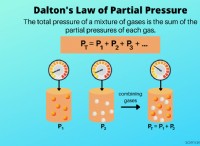Electron(1897): J.J.トムソンは、カソード光線実験を通じて電子を発見し、原子の「プラムプリン」モデルを提案しました。そこでは、電子が正電荷の均一な分布に埋め込まれています。
プロトン(1919): アーネスト・ラザフォードは、彼のゴールドフォイル実験を通じて、原子内の小さく、密な、正に帯電した核の存在を実証しました。この実験中に、プロトンは積極的に帯電した粒子として間接的に検出されました。
中性子(1932): ジェームズ・チャドウィックは、陽子と並んで核に存在する中性粒子である中性子の存在を確認しました。彼の実験では、アルファ粒子でベリリウムを砲撃し、中性放射の放出を観察することが含まれていました。
Positron(1932): カール・アンダーソンは、宇宙線を研究しながら、積極的に帯電した電子であるポジトロンを発見しました。彼は、高エネルギー光子と物質の間の相互作用における電子ポジトロンペアの作成を観察しました。
antiproton(1955): エミリオ・セグレスとオーウェン・チェンバレンは、カリフォルニア大学バークレー校で人工的に最初の反プロトンを生産しました。彼らは、標的と高エネルギーの陽子を衝突させることでこれを達成し、アンチプロトンプロトンペアを作成しました。
nutrino(1956): フレデリック・レインズとクライド・コーワンは、特定の放射性崩壊中に放出される無challでほぼ質量のない粒子であるニュートリノを検出しました。彼らは、ニュートリノの存在を確認するために、逆ベータ崩壊反応を含む実験を実施しました。
Quarks(1964): Murray Gell-MannとGeorge Zweigは、Quarkモデルを独立して提案し、陽子と中性子がクォークと呼ばれるより小さな粒子で構成されていることを示唆しています。この理論は、量子クロモダイナミクス(QCD)の発達と、亜原子粒子の家族への分類につながりました。
これらの発見は、物質の基本的なビルディングブロックの理解に革命をもたらし、粒子物理学の分野に大きく貢献しています。