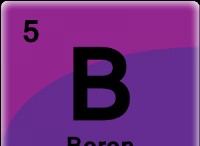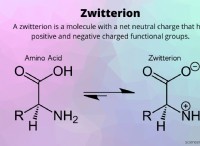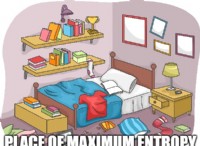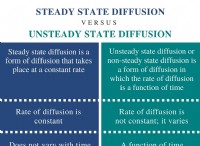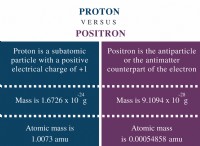1。共有結合: 共有化合物は、原子が最も外側の軌道で電子を共有して安定した電子構成を実現するときに形成されます。
2。分子構造: 結晶格子を形成するイオン化合物とは異なり、共有化合物は離散分子として存在します。
3。電気伝導率: 共有化合物は一般に、電子が局在しており、自由に動くことがないため、固体状態で電気を導入しません。
4。融点と沸点: 共有化合物は通常、分子間の分子間力が弱いため、イオン化合物と比較して溶融点と沸点が低くなります。
5。溶解度: 共有化合物は、極性に応じて、水に可溶性または不溶性のいずれかになります。部分電荷分離を持つ極性共有化合物は、水に溶ける傾向がありますが、非極性共有化合物は水で不可解になります。
6。化学反応性: 共有化合物は一般に、電子の共有がより安定した構成を作成するため、イオン化合物よりも反応性が低くなります。
7。結合強度: 共有結合は通常、水素結合やファンデルワールスの力よりも強いが、イオン結合よりも弱い。共有結合の強度は、原子間で共有される電子ペアの数に依存します。
8。安定性: 共有化合物は一般に、解離しないため、非極性溶媒中のイオン化合物よりも安定しています。
9。可燃性: 炭化水素などの非極性共有化合物は、酸素と容易に反応する炭素炭素結合の存在により、一般に可燃性です。
10。硬度と脆性: 共有化合物は、原子間の共有結合が方向性と剛性であるため、イオン化合物よりも柔らかく脆性である傾向があります。
11。蒸気圧: 共有化合物は、分子間の分子力が弱いため、イオン化合物よりも蒸気圧が高い。
12。揮発性: 共有化合物は、分子間力が低いために容易に蒸発する可能性があるため、イオン化合物よりも揮発性が高いことがよくあります。
13。多型: 共有化合物は、異なる条件下で同じ化合物に対して異なる結晶構造が存在できる多型を示すことができます。