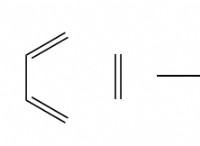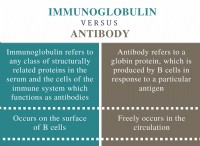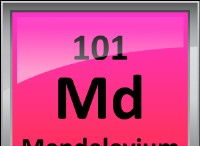コア コンセプト
このチュートリアルでは、2 つの除去反応を区別する 6 つの方法を学びます。 , E1 対 E2 .
このチュートリアルを進める前に、必ず反応自体を理解してください! E1 Elimination と E2 Elimination に関する記事をチェックしてください!
他の記事で取り上げるトピック
- 立体障害
- 酸と塩基の性質
- 強酸と強塩基
- 求核剤
- 求電子剤
語彙
- 中級 – 形成され、反応中に使用される化合物
- 極性プロトン溶媒 – O-H または N-H 結合を含む溶媒
- 立体化学 – 分子内のコンポーネントの物理的な向き
- 立体特異性 – 最初の反応物の立体化学は、分子がどのように反応し、最終生成物の立体化学を決定するかにおいて役割を果たします
- 基板 – 有機反応の開始分子
では、有機化学で E1 反応と E2 反応を区別する 6 つの方法を学びましょう!
1.歩数
E1 と E2 を区別する最も明白な方法は、メカニズムのステップ数を見ることです。 E1 は 2 つのステップで行われ、カルボカチオン中間体があります。一方、E2 は 1 つのステップで行われ、中間体はありません。
2.反応率
E1: これは一次単分子反応であるため、名前の 1 が付けられています。これは、反応速度が基質の濃度のみに依存することを意味します。基質の濃度が上昇すると、反応速度も上昇します。
E2: これは 2 次の二分子反応であるため、名前に 2 が付きます。これは、反応速度が基質と脱プロトン化塩基の両方に依存することを意味します。
3.立体化学
E1: 反応の 2 つのステップが独立して発生するため、分子を空間内で配向する必要がある特定の方法はありません。したがって、E1 には立体特異性がありません。
E2: 切り離される脱離基と水素は、互いにアンチ、つまり 180 度離れている必要があります。これは、反応が 1 つのステップで発生するため、メカニズムの各部分に発生する余地がなければならないためです。このため、この 2 つは空間内で反対の向きにする必要があります。
4.分子の塊
E1: 脱離基を分子に結合している炭素を見ると、かさばるほど E1 脱離が速くなります。 3 次基板が最も速く、2 次基板がそれに続きます。ただし、一次カルボカチオンは不安定すぎて中間体として作成できません (詳細については、ここをクリックしてください)。そのため、この場合、E1 脱離はほとんど発生しません。これは、最も置換されたカルボカチオンが優先されるためです。水素以外の分子との結合が多いほど、安定します。カルボカチオンの安定性は重要です。
E2: E2 も同様の順序に従います。ただし、カルボカチオン中間体がないため、一次基質はこの種の脱離を受ける可能性があります。三次基質が最も優先され、次に二次基質が続き、最後が一次基質になります。

5.基礎力
E1: 求核剤、またはルイス塩基は、強い場合も弱い場合もあります。この反応は 2 段階で行われるため、塩基は脱離基を置換する必要がなく、水素の捕捉のみに集中できます。通常、この反応には水などの弱塩基が適しています。
E2: 水酸化物イオンなどの強塩基が必要です。一段階反応では、極性脱離基の置換を助けるために強塩基が必要です。
6.溶剤
E1: 極性プロトン溶媒は、このタイプの脱離に使用されます。これらのタイプの溶媒はイオン化に適しており、カルボカチオン中間体の安定化に役立ちます。
E2: この反応における溶媒の種類は問題ではありません。
E1 と E2 の反応に関するその他の資料
- Sn1 反応
- Sn2 反応
- Sn1 vs Sn2