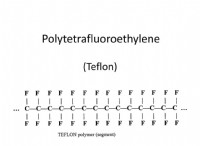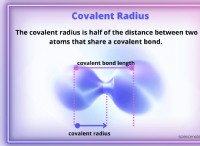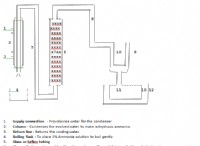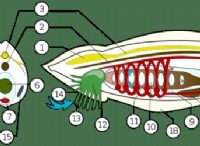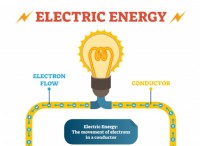有機化学では、超共役は C-H 結合の σ 電子の局在化が起こる安定化反応です。この C-H 結合は、共有されていない p 軌道を持つ原子に直接結合しています。超共役の例は、有機化合物の置換基の p 結合と s 結合の電子間の相互作用です。この記事では、超共役の概念、超共役の意味、および超共役の例について詳しく説明します。
超共役とは?
超共役は、隣接する空のまたは満たされたp軌道またはπ軌道とのσ結合の電子間の相互作用の結果である安定化反応です。これにより、システムの安定性を高める拡張または延長された分子軌道が作成されます。
超共役の概念:
超共役は、ある意味で、エレクトロマー効果に似ています。唯一の違いは、超共役には永続的な効果があるのに対し、エレクトロマー効果は一時的なものであることです。不飽和系の原子または共有されていない p 軌道原子のいずれかに直接結合しているアルカリ基の C-H 結合の電子の局在化は、この効果で発生します。
正電荷の拡散を可能にするグルコースの安定化の理由は、超共役によるものです。正電荷を帯びた炭素原子に結合したアルキル基の数が多いほど、炭酸化の安定化と超共役相互作用が強くなります。
超共役の応用:
超共役にはいくつかのアプリケーションがあります。最も一般的には、ゴーシュ効果、ベータシリコン効果、アノマー効果など、さまざまな化学現象を説明するために使用されます。
超共役は、エタンの回転障壁、置換カルボカチオンと置換炭素中心ラジカルの相対的安定性、環外カルボニル基の振動周波数、およびアルケン安定性に関する熱力学的ザイツェフの法則を説明するためにも使用されます。
超共役効果の種類:
超共役は、大きく 2 つのカテゴリに分けることができます。
等価超共役:
等価超共役は、標準形が電荷分離を示さないフリーラジカルとカルボカチオンで起こります。
犠牲的なハイパーコンジュゲーション:
このタイプの超共役では、正準形は結合共鳴を示さず、主形は電荷分布を持ちません。
解決済みの超共役の例:
質問 1:
次のうち、ベイカー・ネイサン効果を示すものはどれですか?
<オール>解決策:
ベイカー・ネイサン効果は、超共役の別名です。システムの安定性を向上させる細長い分子軌道を与えるために、隣接する空または部分的に満たされた p 軌道または π 軌道との σ 結合 (通常は C-H または C-C) 内の電子の相互作用に焦点を当てた持続的相互作用は、として知られています。超共役。
質問 2:
超共役は非局在化を使用しますか?
<オール>解決策:
結合軌道の非局在化は、超共役に関与しています。これは、システムの安定性を向上させる延長された分子軌道を与えるために、隣接する空または部分的に満たされた p 軌道または π 軌道との σ 結合 (通常は C-H または C-C) に電子が関与する安定した相互作用です。
質問 3:
超共役構造の数が多い、フリーラジカルの安定性
<オール>解決策:
超共役構造の数が多いほど、フリーラジカルの安定性が高くなります。
質問 4:
以下にリストされている状況のうち、ベイカー・ネイサン効果を正しく説明しているのはどれですか?
- 芳香族アルキル ベンゼンのアルキル基の直接的な影響を明らかにするのに役立ちます。
- アルケンの相対的な安定性は、それによって説明できます。
- アルキルカルボカチオンの相対的な安定性は、それによって説明できます。
- 上記のすべて
解決策:
Baker-Nathan 効果は、芳香族アルキル ベンゼンのアルキル基の直接的な影響を説明します。これは、アルケンの相対的安定性とアルキルカルボカチオンの相対的安定性を説明するのに役立ちます。
質問 5:
エテンにはアルファ水素がありません。したがって、超共役は不可能です。
<オール>解決策:
声明は真実です。エテンにはアルファ水素がないため、超共役は不可能です。超共役にはアルファ水素の存在が必要です。
質問 6:
寄与する構造が標準ルイス式と同じ数の 2 電子結合を持っている場合、次のように呼ばれます:
<オール>解決策:
等価超共役は、寄与する構造に標準ルイス式と同じ数の 2 電子結合が含まれる場合に発生します。
質問 7:
α-水素の数を増やすと、超共役構造の数は次のようになります:
<オール>解決策:
答えは選択肢bです。 α-水素の数が増えると、超共役構造の数も増えます。 α-水素の数は、超共役の程度を決定します。官能基に結合している炭素に結合している水素原子は、α-水素として知られています。
結論
この記事では、超共役の概念、超共役の意味、およびその例について詳しく説明しました。超共役は、有機化合物内の隣接分子の C-H 結合の σ 電子の局在化を扱う永続的な効果です。超共役には、等価超共役と犠牲超共役の 2 種類があります。