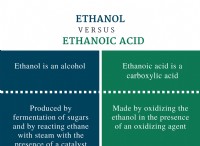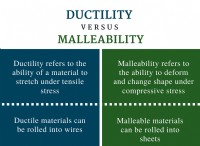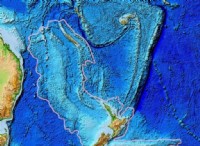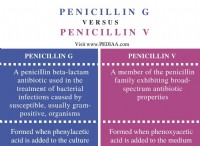2つの主要な減衰経路は、光励起された核酸塩基で競合しています:超高速内部変換(IC)とトリプレットの交差(ISC)はトリプレット状態です。 ICには、同じ電子状態内で過剰なエネルギーが急速に散逸し、通常はフェムト秒内でピコ秒から発生します。一方、ISCは、励起された分子がスピンフリップを受け、一重項からトリプレット状態に移行する遅いプロセスです。トリプレット状態は、一般に一重項状態と比較して長寿命であり、反応性酸素種(ROS)やDNA損傷の形成など、さまざまな光化学反応に参加できます。
光励起された核酸塩基の崩壊が速いか抑制されているかという問題は、広範な研究と議論の対象となっています。初期の研究では、ICが支配的な減衰経路であることが示唆され、核酸塩基がその基底状態に迅速に戻ることを保証し、化学反応を損傷する可能性を最小限に抑えました。しかし、より最近の調査により、ISCは特定の条件下での一部の核塩基、特にグアニンでも効率的に発生する可能性があることが明らかになりました。
いくつかの要因は、光励起された核酸塩基の崩壊ダイナミクスに影響を与えます。
ベーススタッキング: DNAおよびRNAにおける隣接する核塩基の存在は、励起状態の特性と減衰経路に影響を与える可能性があります。積み重ねの相互作用は、ICおよびISCレートを強化または抑制することができます。
溶媒効果: 生物系の水などの周囲の溶媒は、励起状態のダイナミクスに影響を与える可能性があります。溶媒和は、励起状態を安定化または不安定にし、減衰速度を変更する可能性があります。
ベースの変更: 核酸塩基の化学的修飾または突然変異は、電子構造と崩壊メカニズムを変更する可能性があります。修正された塩基は、異なるICおよびISC効率を示す場合があります。
温度と粘度: 温度や粘度などの環境条件は、励起状態の減衰率に影響を与える分子運動と相互作用に影響を与える可能性があります。
核塩基減衰が高速であるか抑制されているかについての議論は、生物系の光化学プロセスの複雑さを強調しています。 ICは多くの核塩基の主要な減衰経路のままですが、特定の文脈で効率的なISCの可能性は、DNAとRNAに対する光誘発効果の全範囲を理解するためのさらなる研究の必要性を強調しています。これらの減衰メカニズムを包括的に理解することは、UV誘導生物学的損傷の分子基盤を解読し、それらの有害な結果を軽減するために戦略を考案するために重要です。